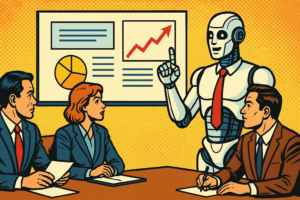中小企業の現場には、ルールがなくても何とかまわってしまう仕事が多くあります。
だからこそ、ルールづくりは「忙しくて手が回らない」「いずれ整えればいい」と、つい後回しにされがちです。
でも、よく見てみると、ルールが無いせいで毎回判断が必要になったり、人によって対応がバラついたり、トラブルが起きるたびに会議が開かれたり……。
本当は考えなくていいはずのことに、貴重な思考力が浪費されているのです。
ルールとは、決まりごとを増やすためのものではありません。
むしろ、「いちいち考えなくて済む状態」をつくることで、“本当に考えるべきこと”に集中できるようにするための仕組みです。
たとえば、お客様への提案、組織の未来、チームの育成、新しい価値づくり。
こうした創造的で本質的な仕事こそ、経営者や後継者が取り組むべき領域です。
でも、現場でルールが曖昧なままだと、どうしても“考えなくていいこと”に引っ張られてしまう。
だからこそ、ルールは「考えないでいい仕組みを先につくる」ために必要なのです。
もうひとつ、大切な視点があります。
ルールを整えるということは、判断を減らすということでもあります。
判断が多い組織は、ミスが増え、ストレスが増え、スピードが落ちます。
逆に、判断を手放すことができれば、組織全体の思考の余白が生まれます。
そしてその余白こそが、「新しいことを考える力」につながっていくのです。
多くの中小企業では、「うちは小さい会社だから」「ベテランがうまくやってくれているから」といった理由で、ルール整備が後回しにされています。
けれどそれは、“たまたま回っている”だけで、“未来に備えて整っている”とは言えません。
トラブルが起きてからルールをつくるのでは遅い。
だから、ルールは“後手”ではなく、“先手”で整えるものなのです。
ルールとは、人を縛るものではなく、人の思考力を守る道具です。
考えたいなら、まず考えなくていいものを、仕組みにしてしまうこと。
それが、後継者として未来を担うあなたにこそ求められる視点ではないでしょうか。。
後継者の学校 代表 大川原